29人の相続人――遺言がなければ大混乱に
先日、こんなご相談をいただきました。
「高齢の叔父が入院中で、余命は長くても1か月ほどと言われています。叔父は『面倒を見てくれているあなたに全部を託したい』と言ってくれているのですが、相続人が誰になるのか分からず不安です」
相談者の方は、叔父さまを長年支えてこられました。しかし相続の仕組みを考えると、「全部を渡す」と言葉で約束しても、その通りにはならない可能性があります。そこで、急ぎ遺言作成を検討することになりました。
叔父さまの家族関係は複雑だった
お話を伺うと、状況は想像以上に複雑でした。
- 叔父さまは90歳を超えるご高齢。ご結婚歴はなく、お子さまもいません。
- 兄弟姉妹は8人いましたが、叔父さまは末っ子で、既に全員他界。
- 幼少期に養子に出ていたため、養子先にも兄弟姉妹が7人いた。
つまり「実家側の相続人」と「養子先側の相続人」が二重に存在するのです。相談者の方も「具体的に何人になるのか、全く分からない」と戸惑っておられました。
病室での公正証書遺言
叔父さまの病状を考えると、残された時間は限られています。
通常、公正証書遺言は公証人と証人2名が同席の下、公証役場で作成しますが、今回は病院に出張してもらう手配をしました。
鹿児島の病院は遠方でしたが、何とか日程を調整し、病室で遺言を作成することができました。
数週間後、叔父さまはご逝去されました。
遺言執行者には当事務所を指名していただいていたため、その後の相続手続きを引き継ぐこととなりました。
相続人は全国に散らばり29人
遺言があるからといって、相続人の調査を省略できるわけではありません。相続登記や預金解約などを行うには、被相続人の戸籍を出生から死亡までたどり、相続人を確定する必要があります。
調査の結果、判明した相続人は――
- 実家側の甥姪:18人
- 養子先の兄弟姉妹:妹1人と、亡くなった兄弟の子ども10人
合計29名。
調査過程で、両親、養母、既に亡くなった兄弟姉妹8人、養子先の亡くなった兄弟姉妹6人の総勢17名の出生から亡くなるまでの戸籍戸籍を収取し、さらにご生存されている相続人29人の現在戸籍の収集も必要でした。
中には、途中、引っ越しで他県に転籍されているかたもいらっしゃり、相続人の戸籍を集めるだけで、全国の役所に問い合わせをし、数十通以上の謄本を取り寄せる大掛かりな作業となりました。
遺言がなければどうなっていたか
29名の相続人の多くは互いに面識がありません。日本全国に散らばって暮らしています。
もし遺言がなかったら、29人全員の合意がなければ遺産を分けることができません。署名・実印・印鑑証明を取り交わし、全員の同意をそろえるのは至難の業。中には「なぜ今さら関わらなければならないのか」と不満を抱く方が出てきても不思議ではありません。場合によっては、相続協議がまとまらず、財産が宙に浮いたまま何年も動かない事態も起こり得たでしょう。
しかし今回は遺言があったおかげで、叔父さまの「面倒を見てくれた人に財産を託したい」という思いがそのまま実現しました。
まとめ
相続は、本人や家族が思っている以上に相続人が広がるケースがあります。特に子どもがいない方の場合、甥姪が20人、30人と相続人になることは決して珍しくありません。
「自分は結婚していないし子どももいないから、相続は簡単なはず」――そんな思い込みが、後に大きなトラブルを呼ぶこともあるのです。
今回の事例は、遺言の有無が相続の行方をどれほど左右するかを、改めて強く示してくれました。
NEWS・COLUMN お知らせ・コラム
-
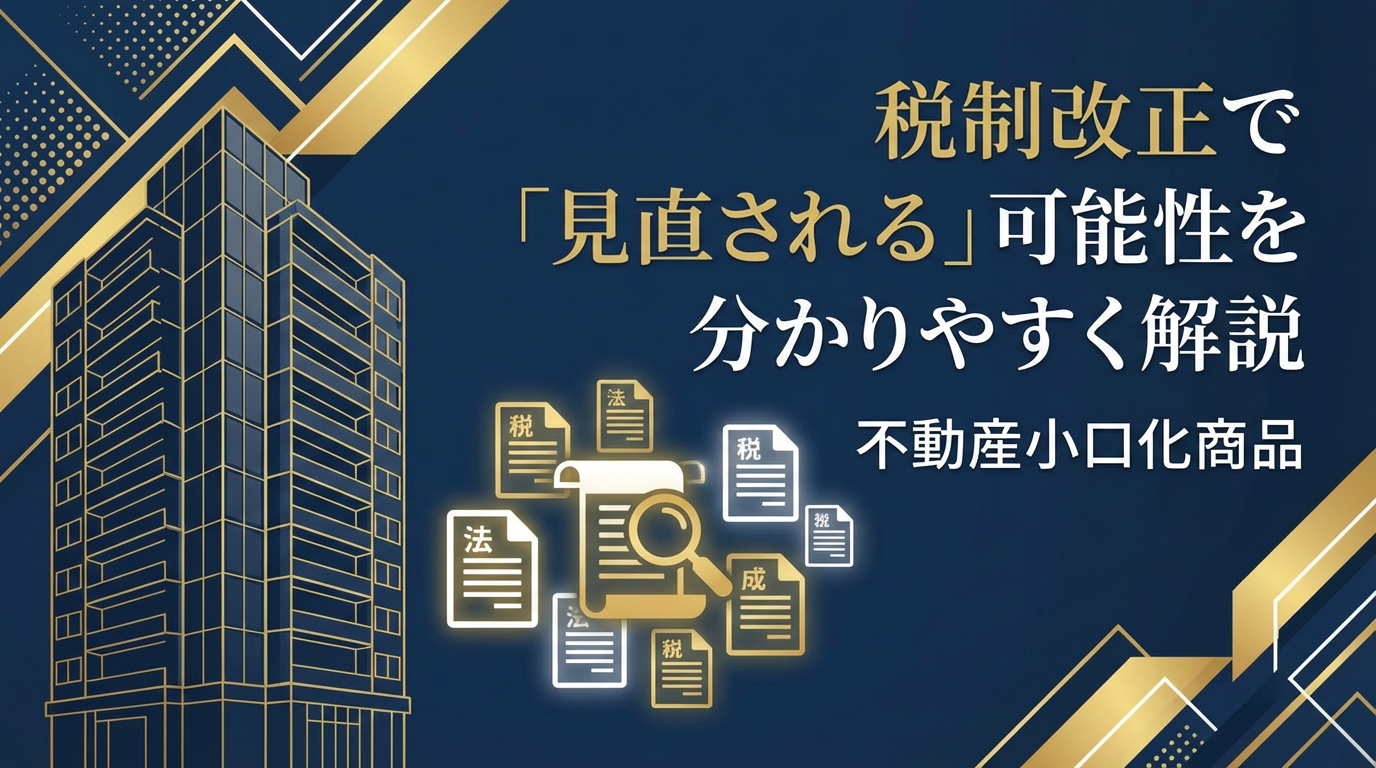
2025.12.14
生前対策
終活
不動産小口化商品による相続対策は今後どうなる?
税制改正で「見直される」可能性を分かりやすく解説相続対策として注目されてきた「不動産小口化商品」について、最近になって「将来、相続対策として使えなくなるのでは?」「無効になるという噂を聞いた」といった声を耳にすることが増 […]
-

2025.9.25
相続
【相続の基礎知識】流れ・手続き・必要書類を徹底解説
相続とは?相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人が受け継ぐことです。財産には不動産・預金・株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続の流れ相続開始(被相続人の死亡)遺言書の確認 […]
-

2025.9.25
生前対策
【生前対策の重要性】相続トラブルを防ぐための賢い準備法
生前対策とは?生前対策とは、自分が元気なうちに財産や生活を整理し、死後に備える準備のこと。日本では相続をめぐる「争族」が社会問題化しており、早めの対策が重要です。生前対策のメリット相続税対策贈与や保険を活用することで、相 […]
