自筆証書遺言があっても安心できない?金融機関での実際のトラブル事例
先日、相続人の方から「遺言があるので、相続の手続きをお願いしたい」とご相談を受けました。
遺言者は、生前にノートへ自筆の遺言を残されていました。全文が手書きで、日付や署名、押印もあり、形式的な要件を満たしているように見えました。
遺言者には子どもがおらず、ご両親やご兄弟も既に亡くなっていたため、晩年の生活を支えてくれた姪2名に財産を残す内容になっていました。
文面は「すべての現金を○○に遺す」といったもの。家庭裁判所で検認手続きを行い、検認済証明書も無事に受け取ることができました。
ところが、ここから思わぬ落とし穴がありました。
遺言者は5つの金融機関に預金を残しており、そのうち4つは遺言を根拠に問題なく解約手続きを進められました。
しかし、1つの銀行だけが「この遺言では当行の『預金』が対象とされているとは解釈できない」として、解約を認めてくれなかったのです。
他の4機関は問題なく手続きができていることを説明し、再度協議をお願いしましたが結論は変わらず、「遺産分割協議書を提出してください」と言われてしまいました。
ここでさらに問題となったのは、疎遠になっていた甥の存在です。遺産分割協議を行うには、その甥を探し出して同意を取り付けなければなりませんでした。
その銀行には約3,000万円の残高があり、遺言どおりなら姪2名で1,500万円ずつを受け取れるはずでしたが、最終的には甥も含めて3名で分けることとなり、一人あたり1,000万円ずつに減ってしまったのです。
自筆証書遺言の基本的な要件
自筆証書遺言は、以下の要件を満たすことで成立します。
- 遺言者が全文を自筆で書く
- 作成した日付を書く
- 戸籍上の氏名をフルネームで書く
- 印鑑を押す
これらをきちんと守っていれば有効とされ、家庭裁判所で検認も受けられます。
しかし、今回のように「文言の解釈」を金融機関が独自に行い、実際の手続きに支障が出ることもあるのです。
専門家に依頼するメリット
遺言は「形式を満たしているかどうか」だけでなく、「解釈の余地を残さない明確な文言」になっているかが非常に重要です。
せっかくの意思が尊重されず、相続人に余計な負担や不利益が生じてしまっては本末転倒です。
当事務所にご相談いただければ、実際の手続きまで想定し、金融機関にも通用する遺言の作成をお手伝いできます。
「作ったはずの遺言が実際には使えない」という事態を防ぐためにも、ぜひ専門家にご依頼ください。
NEWS・COLUMN お知らせ・コラム
-
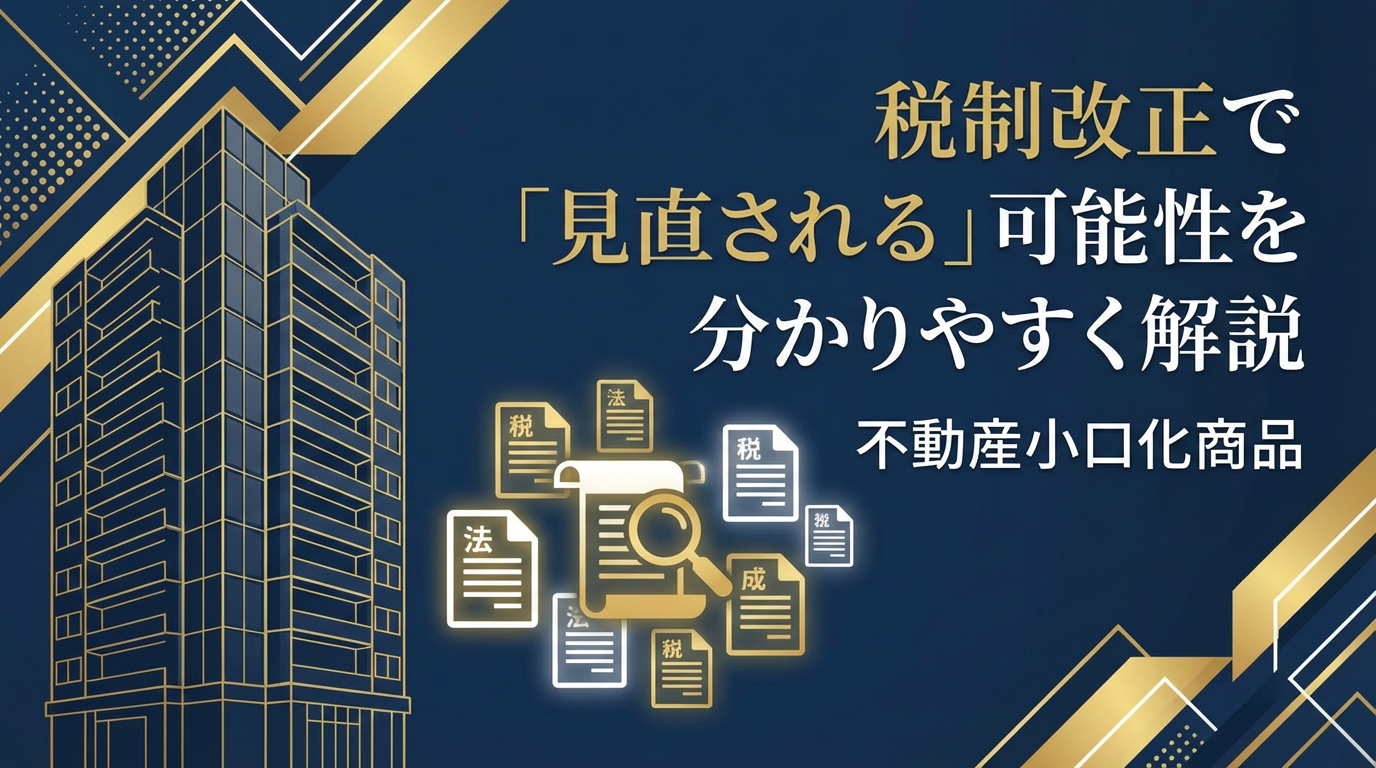
2025.12.14
生前対策
終活
不動産小口化商品による相続対策は今後どうなる?
税制改正で「見直される」可能性を分かりやすく解説相続対策として注目されてきた「不動産小口化商品」について、最近になって「将来、相続対策として使えなくなるのでは?」「無効になるという噂を聞いた」といった声を耳にすることが増 […]
-

2025.9.25
相続
【相続の基礎知識】流れ・手続き・必要書類を徹底解説
相続とは?相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人が受け継ぐことです。財産には不動産・預金・株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続の流れ相続開始(被相続人の死亡)遺言書の確認 […]
-

2025.9.25
生前対策
【生前対策の重要性】相続トラブルを防ぐための賢い準備法
生前対策とは?生前対策とは、自分が元気なうちに財産や生活を整理し、死後に備える準備のこと。日本では相続をめぐる「争族」が社会問題化しており、早めの対策が重要です。生前対策のメリット相続税対策贈与や保険を活用することで、相 […]
