遺言書を法務局に預けられる遺言保管制度|手続き方法をわかりやすく解説
遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に保管する制度のことです。「自筆証書遺言書保管制度」とも呼ばれます。制度の主な目的は、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、相続手続きを円滑に進めることです。遺言保管制度を利用した際の遺言書の保管費用は数千円と安価ですが、安全に保管できます。
本記事では、遺言保管制度のメリットや注意点、具体的な利用方法について紹介します。自宅での遺言書保管と法務局保管の違いを知りたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
遺言保管制度とは
遺言保管制度とは、遺言者が亡くなったあとに遺言内容が確実に実現されるよう、遺言書を法務局に保管する制度のことです。この制度は、2020年7月から開始されました。遺言書は原本と画像データの両方で保管され、法務局が厳重に管理します。対象となる遺言書は、自筆証書遺言のみで、秘密証書遺言は対象外です。
遺言保管制度を利用することで、法務局による形式的な有効性の確認が行われるため、原本の紛失や改ざんを防げます。なお、申請費用は、1件につき3,900円かかります。
遺言保管制度を利用するメリット
遺言保管制度を利用すると、自分で保管する必要がなくなるため、以下のようなメリットがあります。
- 家庭裁判所の検認が不要
- 紛失・盗難を防げる
- 相続開始後に相続人へ通知される
- 遺言書の無効を防ぎやすい
- 公正証書遺言と比べて安価
それぞれのメリットの詳しい内容を見てみましょう。
家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言を自身で保管した場合、相続を開始する際には検認が必要です。しかし、遺言保管制度を利用した場合は、その検認が不要となります。検認は、遺言書が見つかったときにその遺言書が本物であり、かつ内容が改ざんされていないことを確認するために家庭裁判所が行う手続きです。
検認が不要となる理由は、法務局が遺言書を厳重に保管し、相続開始前に形式的なチェックを行うことで、遺言書の内容が一定の確認を受けているとみなされるからです。検認が不要になることで、相続手続きをスムーズに進められます。
紛失・盗難を防げる
遺言保管制度を利用すると、遺言書は法務局で厳重に管理されるため、第三者による盗難や紛失を防げます。また、偽造や改ざんのリスクも軽減可能です。
自宅で遺言書を保管した場合、利害関係者に存在を知られると、内容を書き換えられるリスクがあります。また、紛失を防ぐため、信頼できる第三者に保管を依頼しても、同様のリスクは残ります。
一方、法務局に遺言を預けておけば、遺言者本人以外による内容の閲覧や改変はできなくなり、遺言者の意思を確実に実現できるというわけです。
相続開始後に相続人へ通知される
遺言書は、相続人に発見してもらわないと効力が発生しません。遺言保管制度を利用すれば、一定の条件の下で、遺言保管所が遺言書を保管している旨を、相続人へ通知します。通知の方法には、以下の2種類があります。
| 通知方法 | 概要 |
| 関係遺言書保管通知 | ・相続人等に自筆証書遺言の交付または閲覧をさせたときに通知される ・通知するための手続きは不要 |
| 指定者通知 | ・遺言者が望んだ場合にのみ実施される ・死亡の事実が確認されたら、指定した人へ自動的に通知がいく |
もしも、遺言者が遺言の存在を誰にも知らせていなかった場合、相続人が発見するのは困難です。しかし、遺言保管制度の通知制度を利用すれば、遺言の存在が確実に伝わるため、相続手続きもスムーズに進められます。
遺言書の無効を防ぎやすい
遺言書が無効になりにくいメリットもあります。これは、自筆証書遺言を法務局に提出する際、職員によって遺言書の形式を確認してもらえるためです。
自宅で保管する場合、自分で内容を確認しなければなりません。形式に不備があれば、思いどおりの遺言を実行できなくなる可能性があります。
後述しますが、職員は内容をすみずみまで確認するわけではないので、有効性を保証するものではありません。遺言の有効性を高めたい場合は、行政書士や弁護士などの専門家に、記載内容をチェックしてもらうことをおすすめします。
公正証書遺言と比べて安価
遺言保管制度の利用にかかる費用は、公正証書遺言を作成する場合と比べて安価です。公正証書遺言の作成にかかる費用は、最低でも数万円はかかります。一方、遺言保管制度の利用にかかる費用は、保管手数料の3,900円のみです。
また、公正証書遺言の場合は、行政書士や弁護士などの専門家に依頼すると、さらに費用がかかることも予想されます。作成時にかかる用紙代や筆記用具代を追加したとしても、圧倒的に安いのは遺言保管制度を利用した自筆証書遺言です。
遺言保管制度を利用する際の注意点
遺言保管制度は便利な制度ですが、以下のような利用するうえでの注意点もあります。
- 内容をチェックしてくれるわけではない
- 法務局へ出向く必要がある
- 氏名や住所等の変更時は手続きが必要
それぞれ詳しく解説します。
内容をチェックしてくれるわけではない
遺言保管制度を利用するにあたり、法務局の職員は以下の形式をチェックします。
- 自筆で書かれているか
- 署名捺印されているか
- 日付が書かれているか
このように、法務局では「形式」のみの確認となり、遺言の有効性まで見てくれるわけではありません。当然、アドバイスも受けられないことに留意が必要です。また、職員は遺言の内容に関する相談や質問を受け付けていないため、記載方法に不安がある場合は、行政書士や弁護士などの専門家に依頼する必要があります。
法務局へ出向く必要がある
遺言保管制度を利用する場合は、法務局へ足を運ぶ必要があります。2024年11月現在、遺言書の保管申請は本人しか行えません。代理人が申請することは認められておらず、本人確認を厳密に行うために、法務局で手続きします。また、郵送による申請も不可です。
なお、申請時には以下のような、顔写真付きの身分証明書の提示が求められます。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 運転経歴証明書
- 在留カード
- 特別永住者証明書
有効期限のある身分証明書は、期限内のものが必要です。
病気や怪我の場合、代理申請が認められますが、遺言保管制度はどのような理由であれ、利用できません。ただし、介助者の付き添いは可能です。
氏名や住所等の変更時は手続きが必要
遺言保管制度の申請後に氏名や住所などに変更があった場合は、遺言を保管している法務局に手続きを取る必要があります。遺言者だけでなく、受遺者や遺言執行者、死亡通知人の変更についても同様に手続きが必要です。
とはいえ、変更手続きは義務ではなく、遺言の内容が無効となるわけではありません。ただし、相続の発生時に通知が届かなくなることがあります。
遺言保管制度の利用手続き
遺言保管制度を利用する具体的な手順は、以下のとおりです。
- 遺言書を作成する
- 申請書を作成する
- 必要書類を準備する
- 予約したあと管轄の法務局へ申請する
詳しい手続き内容を見てみましょう。
1. 遺言書を作成する
まずは自筆証書遺言書を作成します。A4用紙と筆記用具を用意し、文面には以下の内容を記載します。
- 日付
- 遺言者指名
- 遺言内容
- 押印
自筆証書遺言は、様式のルールに従って記載する必要があります。自分で作成する場合は、以下の点に注意しましょう。
- 上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白を入れる
- 片面のみに記載
- ページ番号をふる
- ホチキスで綴じない
- 自筆で書く
法務局では遺言書の内容に関する相談には応じられないため、書き方に不安がある場合は、行政書士や弁護士等の専門家に依頼することをおすすめします。なお、法務省のホームページには遺言書の様式例が記載されていますので、こちらも参考にしてみてください。
2. 申請書を作成する
遺言書の次は、申請書の作成です。遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局で保管申請できます。
申請書は、以下の方法で取得可能です。
- 法務省のホームページからダウンロードする
- 最寄りの法務局窓口で入手する
作成での注意点としては、ダウンロードした申請書を使用する場合、そのまま印刷しましょう。申請書は自動読み取り装置で機械処理されるため、拡大や縮小すると正常に処理されません。
3. 必要書類を準備する
申請書を作成したら、以下の必要書類を準備します。
- 顔写真つき身分証
- 遺言者の本籍(外国人は国籍)及び戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し
- 外国語で記載した場合は日本語による本文訳
- 3,900円の収入印紙を貼り付けた申請用紙
- 遺言書
収入印紙は各法務局庁舎内にある販売窓口、もしくは郵便局等で購入できます。
4. 予約したあと管轄の法務局へ申請する
書類の準備が整ったら、予約してから法務局へ申請します。遺言書保管所を決定したら、以下の方法で忘れずに予約しましょう。
- 法務局手続案内予約サービスの専用ホームページ
- 電話予約
- 法務局の窓口で予約
なお、申請日当日の予約はできないので、前日までに済ませておきましょう。当日は、法務局へ必要書類を持参し、申請手続きを行います。
書類に不備等がなければ、保管申請の手続きは当日中に完了です。手続きを終えたら渡される「保管証」は、再発行できないため、なくさないよう注意してください。遺言の存在を家族等に伝えたい場合は、この保管証をコピーして渡しておきましょう。
遺言書の種類
遺言書には、主に以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれの特徴を紹介します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言保管制度を利用できる、唯一の遺言方法です。法的に認められる形式を満たさない場合、無効になります。遺言書は手書きする必要がありますが、財産目録に限り、パソコンでの作成や写しの添付が可能です。
費用があまりかからず、手軽に作成できる点が大きなメリットですが、自宅保管では紛失や盗難、改ざんや隠蔽の恐れがあります。遺言保管制度を利用すると法務局で安全に遺言書を保管でき、家庭裁判所での検認が不要になるため、相続手続きをスムーズに進められます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書のことです。安全性と信頼性が高い遺言形式で、遺言者が口述した内容を基に公証人が作成します。なお作成時には、証人2人以上の立ち会いが必要です。
遺言者の意思や内容が明確であると確認されるため、無効になるリスクが低く、家庭裁判所での検認手続きも不要になるメリットがあります。公証役場で作成され、原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。作成費用は遺産の価額によって異なりますが、確実性を求める場合に最適な選択肢と言えます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密に保ちながら遺言者自身が作成する形式の遺言です。遺言書を作成後、自署して押印し、封筒に入れて封印します。その後、公証人と証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言者が自分の遺言書であることを申述して、手続きが完了です。
内容は秘密にできますが、形式不備がある場合は、無効になるリスクもあります。また、家庭裁判所での検認手続きが必要です。秘密性と信頼性を両立したい場合に適していますが、メリットは少ないため、利用する人は多くありません。
遺言保管制度のよくある質問(FAQ)
ここでは、遺言保管制度でよくある質問についてまとめました。
- Q1. 預けた遺言書を確認する方法はありますか?
- Q2. 公正証書遺言と遺言保管制度はどちらがおすすめですか?
ひとつずつ解説します。
Q1. 預けた遺言書を確認する方法はありますか?
遺言保管制度を利用した場合、遺言者は遺言の内容をいつでも閲覧できます。閲覧方法には以下の2種類があります。
| 閲覧方法 | 特徴 | 費用 |
| モニターによる閲覧 | 全国どこの法務局でも遺言書を確認できる | 1,400円/1回 |
| 原本の閲覧 | 遺言書を預けた法務局のみ、確認できる | 1,700円/1回 |
閲覧する際は、予約してから、請求する必要があります。請求書は法務局のホームページからダウンロードできます。予約は法務局手続案内予約サービスの専用ホームページから、ご登録ください。
なお、相続人は相続が発生してから(遺言者が亡くなってから)でないと、遺言書の内容を確認できません。
Q2. 公正証書遺言と遺言保管制度はどちらがおすすめですか?
公正証書遺言と遺言保管制度には、それぞれ特徴があり、どちらが適しているかは個々のケースやニーズによります。
それぞれの特徴を踏まえたうえで、おすすめの遺言方法を紹介します。
| 遺言の方法 | 向いているケース・ニーズ |
| 遺言保管制度 | ・費用を抑えたい ・相続開始後に相続人へ通知したい ・比較的シンプルな相続である ・相続人同士のトラブルが少ない |
| 公正証書遺言 | ・本人が法務局まで行けない ・有効な遺言書を作成したい ・多額の資産や複雑な条件がある ・自筆による遺言を作成できない |
遺言保管制度の不明点は「遺言の窓口」にご相談ください
遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に預け、紛失や改ざんを防ぎ、相続手続きをスムーズにする制度のことです。
自宅保管との大きな違いは、家庭裁判所の検認が不要となり、相続発生時には相続人に確実に通知されることです。費用も安く、公正証書遺言よりも手軽に利用できます。ただし、法務局の職員による遺言の有効性の確認を受けられないため、内容や書式には念入りなチェックが必要です。遺言保管制度のことで相談したい、不明点を解消したいとお考えであれば、「遺言の窓口」までご連絡ください。遺言の経験豊富な行政書士が、わかりやすく丁寧にサポートいたします。初めての方でも安心してご利用いただける環境を整えておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ARTICLE 記事コンテンツ
-
遺族年金の手続き方法と期限
家族が亡くなった場合、遺族年金を受給できる可能性があります。遺族年金を受け取ることで、今後の経済的な不安を軽減することにつながります。今回は、遺族年金の手続き方法と手続きの期限について、解説していきたいと思います。遺族年 […]
-
遺留分を考慮した生前対策の方法とは
遺留分とは、一定の相続人に認められた、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合のことをいいます。財産を受け渡す側が財産を特定の相続人などに移転させるために、遺留分についてできる対策はどのようなものがあるのでしょうか […]
-
公正証書遺言を作成するメリットと作成手順
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があり、それぞれ法律で定められた手順で作成していく必要があります。今回は、公正証書遺言を作成するメリットと作成手順について解説していきたいと思います。紛失や偽造の […]
NEWS・COLUMN お知らせ・コラム
-
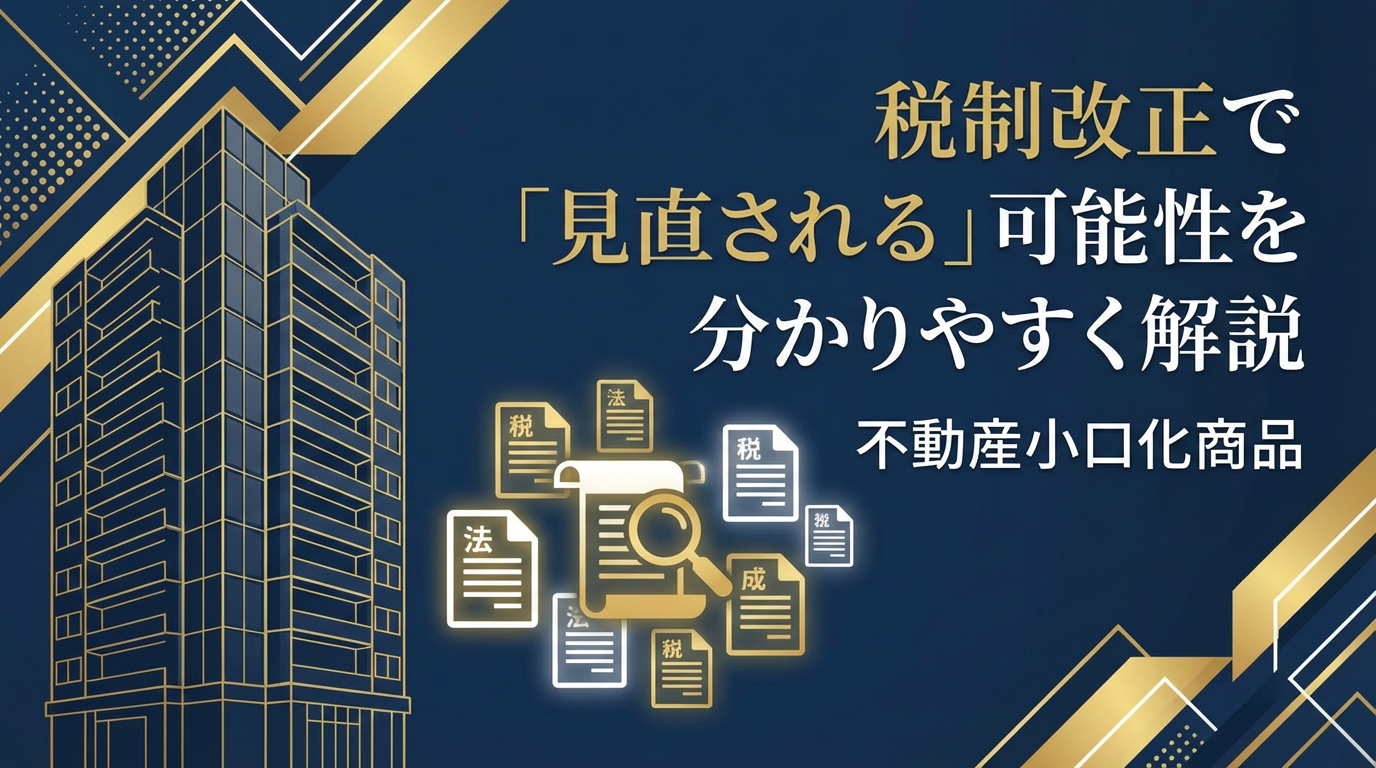
2025.12.14
生前対策
終活
不動産小口化商品による相続対策は今後どうなる?
税制改正で「見直される」可能性を分かりやすく解説相続対策として注目されてきた「不動産小口化商品」について、最近になって「将来、相続対策として使えなくなるのでは?」「無効になるという噂を聞いた」といった声を耳にすることが増 […]
-

2025.9.25
相続
【相続の基礎知識】流れ・手続き・必要書類を徹底解説
相続とは?相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人が受け継ぐことです。財産には不動産・預金・株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続の流れ相続開始(被相続人の死亡)遺言書の確認 […]
-

2025.9.25
生前対策
【生前対策の重要性】相続トラブルを防ぐための賢い準備法
生前対策とは?生前対策とは、自分が元気なうちに財産や生活を整理し、死後に備える準備のこと。日本では相続をめぐる「争族」が社会問題化しており、早めの対策が重要です。生前対策のメリット相続税対策贈与や保険を活用することで、相 […]
