相続権はどこまで?法定相続人の範囲や割合をわかりやすく解説!
相続権とは、亡くなった人(被相続人)から遺産を受け継ぐ、権利のことです。その範囲や適用条件は複雑なため、多くの人が混乱しがちです。相続権をしっかりと把握するには、個人の力だけでは難しいのが現実と言えます。
本記事では、相続権が認められる範囲や相続の割合について、わかりやすく解説します。また、相続放棄や時効といったケースも含めて、詳しく紹介しています。相続の権利でお困りの方や、正しい知識を身に付けたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
一般的に相続権があるのは法定相続人
誰かが亡くなったとき、一般的に相続権が得られるのは、法定相続人です。法定相続人とは、法律で定められた順番や範囲に基づき、遺産を相続する権利を持つ人々のことを指します。
後ほど詳しく解説しますが、配偶者が最優先で次に子どもや孫(直系卑属)、その次に親や祖父母(直系尊属)と続き、最後に兄弟姉妹や甥姪が相続権を持つことになります。この順序に従って、各相続人は遺産の受け取りができるのです。
なお、「相続人」とは相続が発生した際、遺産を取得する人のことです。法定相続人とは異なる意味合いを持っている点に注意しましょう。
遺言書がある場合「受遺者」が遺産を引き継ぐ権利を持つことも
遺言書が存在する場合、「受遺者」にも財産を引き継ぐ権利が与えられることもあります。受遺者とは、被相続人が特定の財産を譲り渡す相手として指定した人物のことです。具体的には、内縁の妻や夫、法人などが挙げられます。受遺者へ遺産を残す場合、「相続」ではなく「遺贈」という形です。
たとえ法定相続人でなくても、受遺者には遺産を受け取る権利があります。ただし、遺言者は「遺留分」と呼ばれる最低限の相続分を、法定相続人に残さなければなりません。遺留分を超えたり下回ったりした場合には、遺言の内容が無効になる可能性もあります。
法定相続人の範囲と相続の割合
遺言書がない場合、法定相続人が遺産を相続します。相続の順位は決まっており、優先順位の高い人が多く相続する仕組みです。相続割合も、順位の高さに応じて異なります。ここでは、法定相続人の範囲とそれぞれの相続割合について説明します。
最優先:配偶者
相続の配分でもっとも優先されるのは、被相続人の配偶者です。配偶者はどのようなケースでも、法定相続人となります。存命であれば、他の相続人がいたとしても必ず遺産を相続します。配偶者の相続分は、以下のとおりです。
| 法定相続人 | 相続の割合 |
| 配偶者のみ | 全て |
| 配偶者と直系卑属 | 1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 |
配偶者は結婚している限り、常に法的に保護される相続権を持つという仕組みです。
一方、内縁の妻や夫は「配偶者」ではないため、法定相続人には該当しません。法定相続人になるには、法律で認められた夫婦である必要があります。たとえ長きにわたって寄り添い続けたとしても、相続はできないということになります。
第1順位:子・孫(直系卑属)
子どもや孫は第1順位で、配偶者の次に優先される法定相続人です。子どもが存命であれば、その子どもが遺産を相続します。すでに子どもが亡くなっている場合、その子(孫のこと)が、「代襲相続人」として相続するのが決まりです。
相続分は、配偶者がいる場合には1/2が子どもや孫で等分され、配偶者がいない場合にはすべての遺産が直系卑属で分配されます。
なお、再婚相手の子ども(実子でない場合)は、血縁関係がないため、法定相続人にはなれません。再婚相手の子どもを法定相続人にするには、養子縁組をする必要があります。
第2順位:親・祖父母(直系尊属)
直系尊属とは、自分より前の世代にあたり、直接的な血縁関係にある親族のことです。この場合、血のつながりがない養父母も、直系尊属に含まれます。
相続における直系尊属の順位は、配偶者や直系卑属に次ぐものです。直系尊属は、配偶者もしくは子どもや孫がいない場合にのみ、相続権を持ちます。その相続分は、1/3を人数分で等分した額です。
なお、直系尊属に代襲相続の適用はありません。直系尊属がいなければ、次に解説する第3順位に相続権が移ります。
第3順位:兄弟姉妹・甥姪
兄弟姉妹は、配偶者もしくは子どもや孫、親がいない場合にのみ、相続権を持ちます。兄弟姉妹や甥姪は相続順位がもっとも低く、他の法定相続人がいる場合は相続権が発生しません。
相続分は、1/4を人数分で等分した額です。もしも兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子どもである甥姪が代襲相続人として相続権を持ちます。
法定相続人が相続できる割合(法定相続分)
法定相続分とは、法律で定められた相続人ごとの遺産分配の割合のことです。遺言書がない場合、法定相続人はこの割合に基づいて遺産を受け取ります。遺産分割の基準としては、相続人の優先順位と人数によって異なります。
ここでは、1,000万円相続するとして、法定相続分の計算方法と遺留分について、具体例を3つ出しながら解説します。
例1. 配偶者と子ども2人の場合
配偶者と子ども2人が相続人である場合、法定相続分は配偶者が1/2、子ども2人がそれぞれ1/4ずつとなります。
配偶者は常に一定の割合で相続し、残りの遺産を子どもたちで分け合う形です。よって、配偶者は500万円、子ども2人はそれぞれ250万円を受け取ることになります。
遺留分については、以下のとおりです。
- 配偶者:法定相続分の1/2 = 500万円 × 1/2 = 250万円
- 子ども1人あたり:法定相続分の1/2 = 250万円 × 1/2 = 125万円
例2. 子ども1人と孫4人の場合
被相続人の子どもが1人と孫が4人の場合、子どもの法定相続分は全財産の100%です。そのため、1,000万円すべてが子どもに相続されます。遺産分割のルールでは、子どもが生存している場合、孫は法定相続人にはなりません。
続いて遺留分ですが、これは子ども1人の場合、法定相続分の1/2となります。つまり、遺留分は500万円(1,000万円 × 1/2)です。
例3. 配偶者と兄弟姉妹が1人の場合
配偶者と兄弟姉妹1人が相続人となるケースでは、配偶者が遺産の3/4を、兄弟姉妹が1/4を相続します。具体的な金額は以下のとおりです。
- 配偶者:1,000万円 × 3/4 = 750万円
- 兄弟姉妹:1,000万円 × 1/4 = 250万円
なお、遺留分については、上記の2例とは事情が異なります。兄弟姉妹には遺留分請求権がないため、遺言などで別の分配がなされた場合でも、遺留分に関する主張はできません。
また、配偶者は遺留分請求権があり、1,000万円 × 3/4 × 1/2 = 375万円を請求する権利があります。遺留分の有無に十分注意しましょう。
相続の時効とは
相続の権利に関する時効は存在しません。そのため、相続発生から何年後であっても、相続権が消滅することはないのです。しかし、相続のさまざまな手続きには、時効があります。手続きを放置していると、手遅れになり、相続できなくなってしまうこともあります。
相続の手続きに関する、主な手続きの期限は以下のとおりです。
- 相続回復請求権の時効:5年(最長20年)
- 遺留分侵害額請求権の時効:1年(最長10年)
- 相続放棄できる期限:3カ月
- 相続税申告の時効:10か月以内
- 相続登記の時効:不動産の取得を知ってから3年以内
最短の手続きである相続放棄は、遺言者が亡くなってから3か月以内に済ませなければならないものもあります。相続が始まると何かと忙しくなるため、早めの対応を心がけましょう。
法定相続人でも相続権がないケース
たとえ法定相続人であっても、一定の条件下では相続権を失うことがあります。それが以下の3つです。
- 相続放棄
- 相続欠格
- 相続廃除
それぞれのケースについて見てみましょう。
相続放棄
相続放棄とは、法定相続人が自らの意思で相続権を放棄する手続きのことです。遺産におけるプラスの財産だけでなく、負債も含めた一切の相続を受けないことになります。
相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。3か月を過ぎると、単純承認(プラス・マイナスの財産をすべて相続すること)しか選択できなくなってしまうため、注意しましょう。
また、相続放棄を選ぶと、初めから相続人でなかったものとして扱われるため、その後の相続争いに巻き込まれる心配はありません。一方で、プラスの財産も相続できなくなってしまう点には注意が必要です。
相続欠格
相続欠格とは、法定相続人が重大な犯罪行為を行った場合などに、法律上相続権を失うことです。具体的には、以下の事由により相続欠格となります。
- 故意に被相続人又は他の相続人を殺害した、又は殺害しようとしたために、刑に処せられた場合。
- 被相続人の殺害人物を知りながら告発せず、又は告訴しなかった場合。(ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。)
- 被相続人を騙したり脅したりして、その人の遺言に関する決定を妨げた場合。
- 被相続人を騙したり脅したりして、その人に遺言を作らせたり、変更させたり、取り消させたりした場合。
- 相続に関する遺言書を勝手に作り替えたり、隠したり、故意に紛失させたりした場合。
相続欠格が適用されると、法定相続人は自動的に相続権を失います。よって、他の法定相続人が代わりに遺産を受け取ることになります。また、相続欠格に該当した場合、遺留分は認められません。
相続廃除
相続廃除とは、被相続人が特定の相続人に対して相続権を剥奪することです。相続廃除は、生前もしくは遺言書にて手続きを取り、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続廃除の理由には、被相続人に対する虐待や重大な侮辱行為、著しい非行などが挙げられます。単に「お互いに馬が合わないから」「なんとなく気に入らないから」などの安易な理由では認められません。
例えば、相続人が被相続人に対して毎日暴力を振るっていた場合のように、客観的に見ても明らかに問題があると判断されるケースは、家庭裁判所が相続廃除を決定します。相続廃除が認められると、その相続人は遺産を受け取る権利を失い、他の相続人がその分を相続します。
相続権に関するよくある質問
相続に関する手続きは非常に複雑なため、疑問が生じることも少なくありません。
ここでは、特に多く寄せられる3つの質問について解説します。
Q1.養子は法定相続人になれる?
結論から言うと、養子も法定相続人として認められます。たとえ血縁関係がなくても。養子とは法律上の親子として認められているためです。養子は実子と同じ権利を持ち、相続分も同じ割合となります。ただし、養子の種類によっては相続の権利が変わってくるため、注意が必要です。
例えば、普通養子縁組の場合は、養親と実親の両方の相続権が発生します。しかし、特別養子縁組では、実親の相続権が完全に消滅します。このように、養子の種類や状況により相続権の扱いが異なるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
Q2.相続人が行方不明の場合はどうなる?
相続人が行方不明の場合、その人自身が相続手続きを行えません。この場合、他の相続人や利害関係者は家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらうことで、相続を進められます。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する責務を負います。つまり、行方不明者の相続人に代わって相続手続きを代替的に行う、いわば代理人のような存在です。
また、行方不明者が7年以上消息不明であれば、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが可能です。これによって、行方不明の相続人は法的に死亡したものとみなされ、遺産分割協議の参加は不要となります。
Q3.法定相続情報一覧図は誰でも取れる?
法定相続情報一覧図とは、相続人からの相続関係を一覧に表した表のことで、相続手続きにおいて非常に便利で役立つ書類です。
この法定相続情報を取得できるのは、以下の人々です。
- 相続人
- 相続人から取得を委任された親族
- 相続人の代理人(行政書士・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・海事代理士・弁理士)
戸除籍謄本の代わりとして、相続登記に相続関係を証明する書類として利用できるため、相続の手続きを簡素化できます。
なお、法定相続情報一覧図の取得自体は無料でできますが、代理人に依頼した際は別途費用がかかります。
相続に関するお悩みは「相続の窓口」へご相談ください
相続権は、被相続人の家族構成や関係性などによって複雑になりがちです。特に兄弟姉妹が多いなどの場合は、より相続権がややこしくなってしまうでしょう。無理に自力で何とかしようとせず、専門家の力を借りて解決することをおすすめします。
広島・福山・北大阪で、相続に関するご相談をご希望であれば、「相続の窓口」におまかせください。相続に特化した行政書士が、手続きや書類の作成を承ります。まずはお気軽にご相談ください。
ARTICLE 記事コンテンツ
-
遺族年金の手続き方法と期限
家族が亡くなった場合、遺族年金を受給できる可能性があります。遺族年金を受け取ることで、今後の経済的な不安を軽減することにつながります。今回は、遺族年金の手続き方法と手続きの期限について、解説していきたいと思います。遺族年 […]
-
遺留分を考慮した生前対策の方法とは
遺留分とは、一定の相続人に認められた、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合のことをいいます。財産を受け渡す側が財産を特定の相続人などに移転させるために、遺留分についてできる対策はどのようなものがあるのでしょうか […]
-
公正証書遺言を作成するメリットと作成手順
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があり、それぞれ法律で定められた手順で作成していく必要があります。今回は、公正証書遺言を作成するメリットと作成手順について解説していきたいと思います。紛失や偽造の […]
NEWS・COLUMN お知らせ・コラム
-
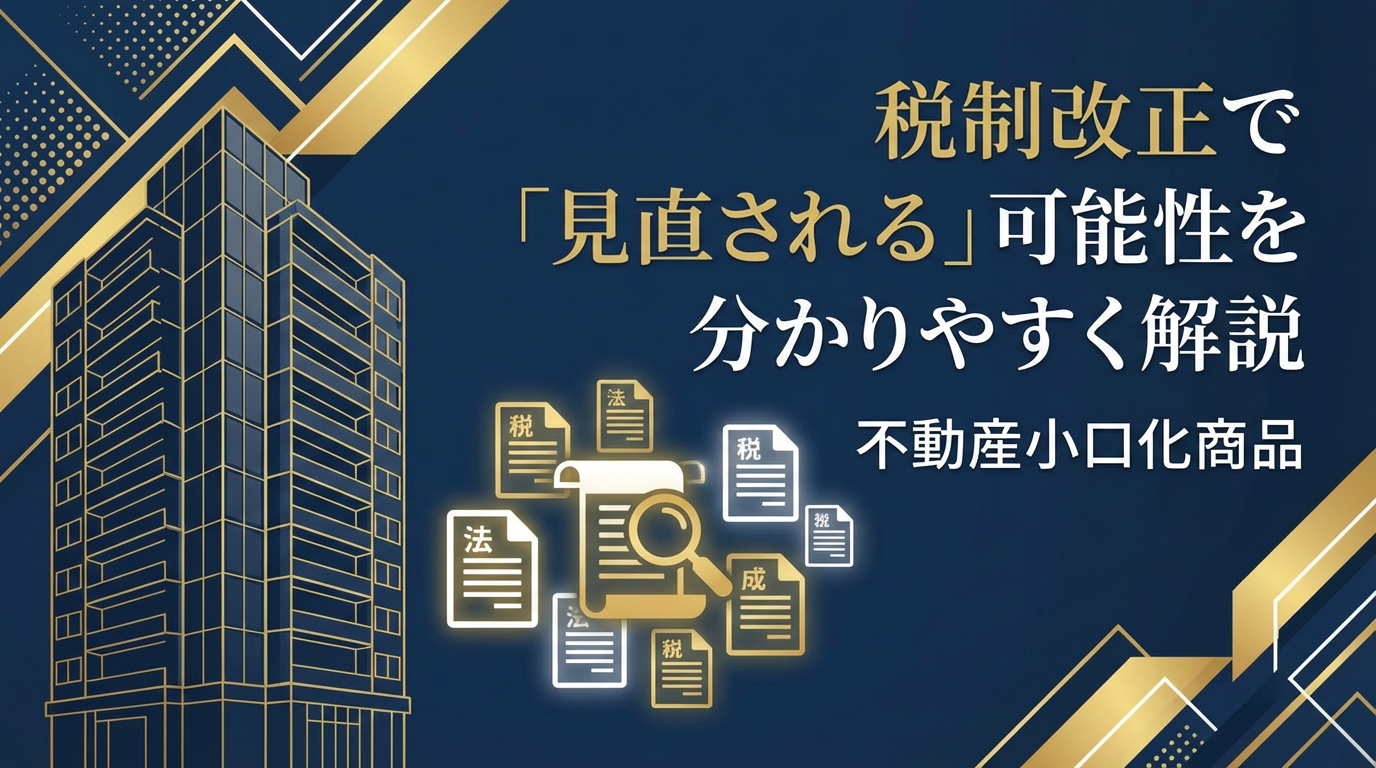
2025.12.14
生前対策
終活
不動産小口化商品による相続対策は今後どうなる?
税制改正で「見直される」可能性を分かりやすく解説相続対策として注目されてきた「不動産小口化商品」について、最近になって「将来、相続対策として使えなくなるのでは?」「無効になるという噂を聞いた」といった声を耳にすることが増 […]
-

2025.9.25
相続
【相続の基礎知識】流れ・手続き・必要書類を徹底解説
相続とは?相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人が受け継ぐことです。財産には不動産・預金・株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続の流れ相続開始(被相続人の死亡)遺言書の確認 […]
-

2025.9.25
生前対策
【生前対策の重要性】相続トラブルを防ぐための賢い準備法
生前対策とは?生前対策とは、自分が元気なうちに財産や生活を整理し、死後に備える準備のこと。日本では相続をめぐる「争族」が社会問題化しており、早めの対策が重要です。生前対策のメリット相続税対策贈与や保険を活用することで、相 […]
