相続不動産の登記手続きとは?必要書類や費用目安についても解説
令和6年4月から、不動産の相続登記の義務化が始まりました。相続の発生を知ってから3年以内に手続きする必要があります。もしも手続きを怠ると、過料の発生や売却したくてもできなくなるなど、さまざまなリスクがあります。
本記事では、不動産の相続登記の手続きや費用目安、専門家に依頼すべきケースなどについて解説しています。相続登記の手続きをしなければならない方、具体的な方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
不動産の相続登記とは
不動産の相続登記とは、その不動産を所有していた人が亡くなった際に、名義を相続人へ変更する手続きのことです。いわゆる「相続を原因とする所有権移転登記」です。
不動産に関する持ち主の情報は、法務局にある登記事項証明書(登記簿謄本)で管理されています。もしも所有者が亡くなった場合は、相続が発生してから3年以内に相続登記をすませる必要があります。
相続登記を怠ると、所有権の移転が証明されません。すると、不動産の売買ができなくなったり、相続人のあいだでトラブルがおきたりと、さまざまなデメリットが発生します。
不動産の相続登記における義務化とは
令和6年4月1日、不動産の相続登記が義務化されました。義務化の背景には、「所有者不明土地」の問題があります。所有者不明土地とは、所有者が不明か、所有者は判明しているものの連絡が取れない状態の土地のことです。
土地の所有者が不明だと、適切な管理が行われず、その土地だけでなく周囲の環境も悪くなる可能性があります。さらに、土地の買取交渉ができないため、有効活用ができなくなるといった問題も生じます。このような所有者不明土地の問題を解消するために、これまで任意だった不動産の相続登記が義務化されました。
対象となるのは、相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)で、過去に相続した不動産も含まれます。
不動産の相続登記に必要な書類一覧
不動産の相続登記では、さまざまな書類が必要となります。
| 書類 | 取得場所 | 法定相続分 | 遺言書がある場合 | 遺産分割協議の場合 |
| 登記申請書 | 要 | 要 | 要 | |
| 委任状 | ケースによる | |||
| 相続関係説明図 | ケースによる | |||
| 遺言 | 要 | |||
| 遺産分割協議書 | 要 | |||
| 被相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 要 | 要 | 要 |
| 被相続人の除籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 要 | 要 | |
| 被相続人の改製原戸籍 | 本籍地の市区町村 | 要 | 要 | |
| 被相続人の住民票の除票 | 住所地の市区町村 | 要 | 要 | 要 |
| 相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 要 | 要 | 要 |
| 相続人の印鑑証明書 | 住所地の市区町村 | 要 | ||
| 相続人の住民票 | 住所地の市区町村 | 要 | 要 | |
| 相続人の課税明細書または固定資産評価証明書 | 毎年4月頃に市区町村から送付 | 要 | 要 | |
委任状は、代理人による申請が行われる場合に必要となります。また、相続関係説明図が必要となるのは、戸籍・除籍謄本の原本の還付を希望する場合です。
不動産の相続登記手続き
不動産の相続登記手続きは、主に以下のような流れで行われます。
- 相続する不動産を確認する
- 遺言または遺産分割協議で相続人を決める
- 相続登記に必要な書類を収集する
- 相続登記申請書を作成・申請する
- 管轄の法務局へ申請する
一つずつ見てみましょう。
1.相続する不動産を確認する
まずは、被相続人が所有していた不動産を確認しましょう。法務局から登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することで、不動産の所有者や抵当権の設定状況を確認できます。
登記事項証明書の取得方法は、次の2種類です。
- 登記所の窓口で直接請求する
- オンラインで請求する
オンライン請求では、最寄りの登記所か法務局証明サービスセンターでの受け取り、または郵送を選べます。窓口での請求よりも手数料が安く、午後9時まで請求できるなどのメリットがあります。なお、相続する不動産が複数ある場合は、すべての物件をもれなく確認しましょう。
2.遺言または遺産分割協議で相続人を決める
不動産の確認後、次は相続人を確定しましょう。遺言があれば、その内容に従って不動産の相続人が決まります。
遺言がない場合や内容に不備がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。その際、全員の合意が必要です。合意に至らない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判に発展する可能性があります。
なお、相続放棄した場合は、遺産分割協議に参加しなくても構いません。相続人が遠方に住んでいる場合は、電話やメールでの意思確認でも認められます。遺産分割協議で全員の同意を得られたら、遺産分割協議書を作成します。
3.相続登記に必要な書類を収集する
相続人が決まったら、必要な書類を揃えましょう。一般的に、相続登記で必要な書類は、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄本や登記事項証明書などです。上記で詳しく解説しているので、参考にしてください。
主な書類は、役所で取得できます。書類の収集には時間がかかるため、できるだけ早く準備を進めておくことをおすすめします。
4.相続登記申請書を作成する
書類を収集したら、相続登記申請書を作成しましょう。申請書の決まったフォーマットはなく、A4サイズの用紙を使用してください。作成は手書きでもパソコンでも構いませんが、鉛筆は使用不可です。
法務局のホームページでは雛形がダウンロードできます。記載すべき内容が書かれているので、参考にしてください。作成できたら添付書類と共に左とじにして、法務局へ提出します。
5.管轄の法務局へ申請する
相続登記申請書が完成したら、相続する不動産が所在する地域を担当する法務局へ申請しましょう。申請方法には、以下の3種類があります。
- 窓口への持参
- 郵送
- オンライン申請
郵送は、書類をそろえて法務局へ書留で送る方法です。封筒には「不動産登記申請書在中」と記載します。登記完了時に還付を希望する書類及び登記完了証の返却が必要な場合は、返信用封筒と切手を同封しておきましょう。
オンライン申請では、スキャンした書類データを一度法務局へ送信し、後ほど原本も送付する(もしくは直接持参)する必要があります。なお、申請時には登録免許税の支払いも必要です。費用の詳細については、以下で解説します。
不動産の相続登記にかかる費用
不動産の相続登記にかかる費用は、以下のとおりです。
- 必要書類の取得費用
- 登録免許税
それぞれ詳しい内容を見てみましょう。
必要書類の取得費用
相続登記には、さまざまな書類が必要です。自治体によって異なるものもありますが、それぞれの費用は以下のとおりです。
- 戸籍謄本:450円
- 除籍謄本:750円
- 改製原戸籍謄本:750円
- 戸籍の附票の写し:300円
- 住民票:約150~500円
- 固定資産税評価証明書:約200~400円
- 印鑑証明書:約200~300円
1通あたりの費用は少額ですが、複数の証明書が必要となります。例えば、必要な戸籍謄本の数は、シンプルな相続の場合でも5〜10通程度になることが一般的です。
登録免許税
不動産登記の際には、登録免許税を納める必要があります。相続における登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。例えば、評価額が1,000万円の不動産なら、登録免許税は4万円です。
なお、不動産の評価額が100万円以下の場合は、免税されます。この場合、申請書の登録免許税の欄には、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載してください。
また、1次相続で相続登記しないまま相続人がなくなり、2次相続の相続登記をする際は、1次相続にかかる登録免許税が免除されます。
専門家に依頼する場合の費用目安
相続登記を専門家に依頼する場合、一般的な費用相場は5万〜15万円です。ただし、この費用はあくまでも目安ですので、必ずしもこの金額内に収まるというわけではありません。
依頼費用を少しでも抑えるコツは、以下のとおりです。
- 書類は自分でそろえる
- 遺産分割協議書や相続登記の書類申請書を自分で作成する
なお、不動産の数や相続する金額、法定相続人数や書類収集する戸籍の数によって、費用は大きく異なります。他にも相続関係が複雑になっている場合(数次相続・養子縁組・代襲相続など)も、費用を加算されることが多いでしょう。
不動産の相続登記を放置した場合のリスク
不動産の相続登記を放置した場合、以下のようなリスクが発生します。
- 不動産の売却ができなくなる
- 担保提供ができなくなる
- 相続問題が複雑化する
- 過料が発生する
それぞれ詳しく見てみましょう。
不動産の売却ができなくなる
不動産の相続登記を怠ると、不動産を売却できなくなる可能性があります。
所有者が亡くなっても、名義変更が行われない土地や建物を「相続登記未了」と言います。相続登記未了の不動産は、登記簿上の名義と実際の所有者(売主)が異なるため、買主への所有権移転ができず、原則として売却できません。
相続登記未了でも、不動産会社によっては売却を依頼できる場合があります。しかし、実際に売買が行われるまでには相続登記を済ませておく必要があります。
担保提供ができなくなる
所有者と登記簿の名義が異なっている場合、不動産を担保にした融資を受けられません。実際の所有者と登記簿上の所有者は、一致している必要があるためです。不動産を担保にして融資を受けたい場合は、相続登記手続きをする必要があります。
一方で、抵当権がついている不動産を相続する場合は、相続放棄を検討する方法もあります。抵当権の内容は、登記事項証明書で確認可能です。抵当権がついている場合、「所有権以外の権利に関する事項」の欄に、内容が書かれているため、あわせて確認しておくと良いでしょう。
相続問題が複雑化する
不動産の相続登記を放置すると、相続問題が複雑化する恐れがあります。例の一つに「相続人の増加」があります。相続人が次の世代へと移り変わると相続人の数が増え、登記手続きの際に必要な書類や手続きが増えてしまうのです。
何代にもわたって放置された不動産は、正確な持分がわからなくなり、専門家でも相続登記の手続きが困難になります。すると、依頼した際により多くの費用が発生することも考えられます。
過料が発生する
不動産の相続登記を行わないと、過料が発生する可能性があります。相続登記の義務化に伴い、不動産取得を知った日から3年以内に、相続登記の手続きを行わなければなりません。正当な理由がないまま手続きを怠ると、10万円以下の過料が発生する可能性があるのです。
この場合の正当な理由とは、以下のようなケースを指します。
- 相続人が多数で、手続きに時間がかかる場合
- 相続人のあいだで争いがある場合
- 相続人に病気等の事情がある場合
- 相続人に生命・心身の危害が及ぶ恐れがある場合
- 経済的困窮により登記申請費用を負担できない場合
シンプルな相続登記なら自分手続きできることも
相続手続きは、内容や相続人の関係がシンプルな場合は、自分で相続登記の手続きを行えることもあります。例えば、以下のような状況が挙げられます。
- 基本的な相続である
- 日中に役所へいける環境がある
- 相続人同士の関係が良好
- 特殊な遺産分割がない
- 労力をかけられる気力がある
自分で相続登記を行う場合のメリットとデメリットをふまえ、自身の状況に向いているかどうかを判断しましょう。
自分で相続登記を行うメリット
自分で相続登記を行うメリットは、主に費用を節約できることです。
専門家へ依頼すると、報酬だけでなく、書類を取得するための費用や交通費などの諸経費が発生します。自分で相続登記を行えば、必要最低限の費用だけで手続きを進められるのです。書類の取得費用や登録免許税は避けられませんが、司法書士や弁護士への依頼料が不要になります。
また、急がない場合や内容が簡単なケースでは、自分のペースで進められるメリットもあります。
自分で相続登記を行うデメリット
自分で相続登記を行う場合、以下のようなデメリットがあります。
- 手続きに時間や手間がかかる
- 登記もれやミスのリスクが発生する
相続登記では、複雑な書類作成や証明書の準備が必要となり、法律的な知識がないと理解しにくい部分も多くあります。また、登記内容に誤りがあると、後から修正手続きを行わなければならず、さらに時間と労力がかかる可能性もあるのです。
不動産の相続登記を専門家に依頼すべきケース
不動産の相続登記は、次のように相続の内容が複雑であれば専門家に依頼した方が良いでしょう。
- 複雑な相続関係や未登記の不動産がある場合
- 相続人が多忙で手続きを進められない場合
- 早急に登記を完了させたい場合
具体的なケースを以下で紹介します。
複雑な相続関係や未登記の不動産がある場合
複雑な相続関係、未登記の不動産がある場合は、専門家に依頼するのが得策です。複雑な相続関係とは、以下のようなケースを指します。
- 数次相続や代襲相続が行われた場合
- 愛人の子どもなど、相続人の関係が複雑な場合
- 遺産分割協議が難航しそうな場合
相続人の関係性がややこしくなるほど、手続きは煩雑になります。また、申請に間違いがあった場合は「更生登記」という別の手続きが必要となり、二度手間となります。このように、複雑な相続手続きを必要とする場合は、専門家への依頼がおすすめです。
相続人が多忙で手続きを進められない場合
仕事や育児など、相続人が忙しく手続きを進められない場合も、専門家へ依頼したほうが良いでしょう。
相続の手続きでは、法務局や市区町村の役所へ足を運ぶ必要があります。一部の役所では、日曜日に開庁しているところもありますが、公的機関のため、基本的には平日の日中しか対応してもらえないところも多いでしょう。
そのため、土日しか動けない人や平日休みを取れない人にとっては、必要書類を取得するのが難しくなります。
専門家に依頼すれば、費用はかかりますが、確実に手続きを進められます。多忙な方にとっては、時間と労力を節約できる選択肢となるでしょう。
早急に登記を完了させたい場合
できるだけ早く相続登記の手続きを完了させたい場合も、専門家に依頼することをおすすめします。登記手続きには、さまざまな書類が必要となり、細かい要件が伴うものです。もしも、自分で手続きをして、書類の内容に誤りや不足があると、手続きが遅れる恐れもあるのです。
さらに、相続登記の手続きは人生において頻繁に行われるものではないため、役所とのやりとりに不慣れで時間がかかることもあります。専門家に依頼すれば、そのような問題を避けられ、スムーズに手続きを進められます。
早急に相続登記を済ませたい場合や時間的制約がある場合は、専門家に依頼することで、効率的かつ確実に手続きを終えられるでしょう。
不動産の相続手続きでお困りの際は「相続の窓口」へ!
不動産の相続登記は、相続が発生した場合に必ず行わなければなりません。相続登記を怠ると、過料が発生したり、不動産の売却ができなくなったりと、さまざまなデメリットが生じやすくなります。相続登記の手続きは自分で行うことも可能ですが、相続関係が複雑な場合は専門家への依頼がおすすめです。「相続の窓口」では、相続に特化した行政書士が、さまざまな相続のケースに対応いたします。まずは無料相談からお問い合わせください。
ARTICLE 記事コンテンツ
-
遺族年金の手続き方法と期限
家族が亡くなった場合、遺族年金を受給できる可能性があります。遺族年金を受け取ることで、今後の経済的な不安を軽減することにつながります。今回は、遺族年金の手続き方法と手続きの期限について、解説していきたいと思います。遺族年 […]
-
遺留分を考慮した生前対策の方法とは
遺留分とは、一定の相続人に認められた、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合のことをいいます。財産を受け渡す側が財産を特定の相続人などに移転させるために、遺留分についてできる対策はどのようなものがあるのでしょうか […]
-
公正証書遺言を作成するメリットと作成手順
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があり、それぞれ法律で定められた手順で作成していく必要があります。今回は、公正証書遺言を作成するメリットと作成手順について解説していきたいと思います。紛失や偽造の […]
NEWS・COLUMN お知らせ・コラム
-
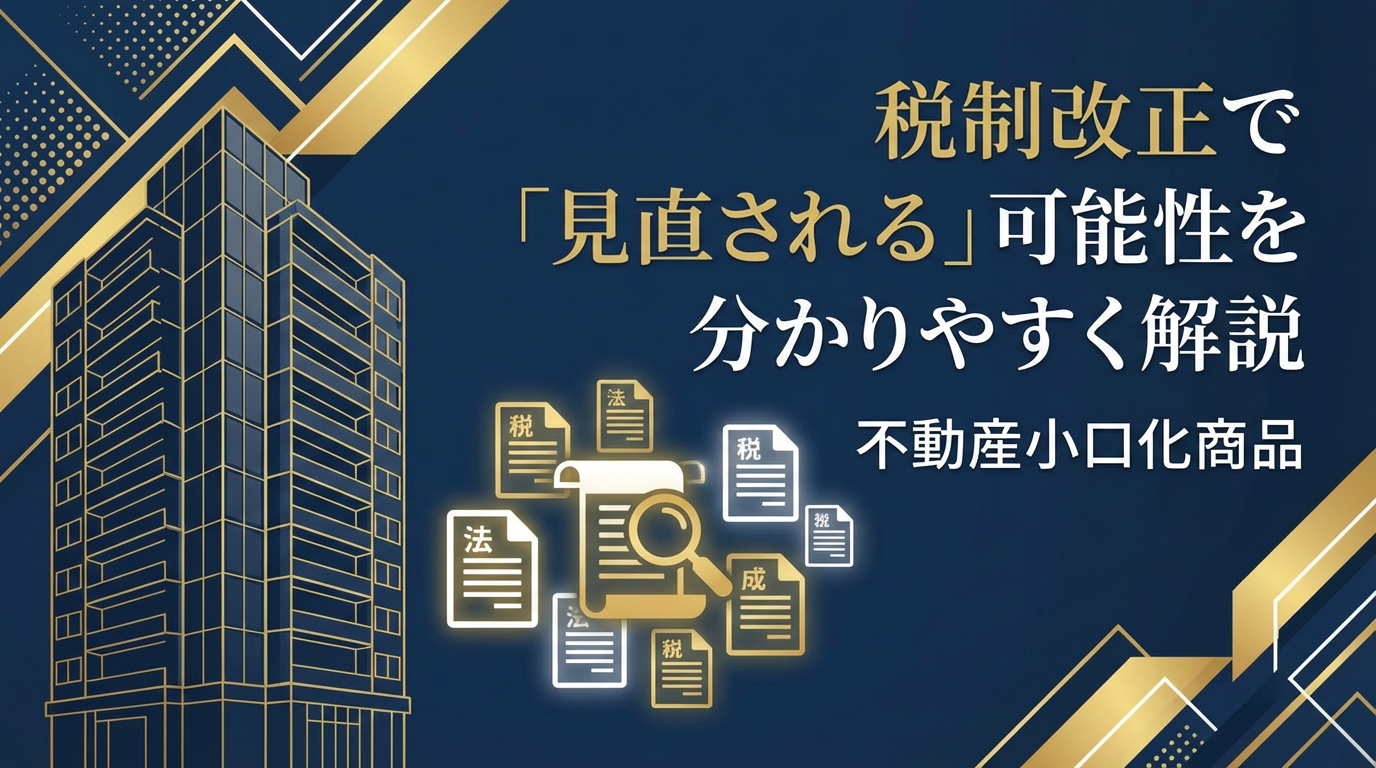
2025.12.14
生前対策
終活
不動産小口化商品による相続対策は今後どうなる?
税制改正で「見直される」可能性を分かりやすく解説相続対策として注目されてきた「不動産小口化商品」について、最近になって「将来、相続対策として使えなくなるのでは?」「無効になるという噂を聞いた」といった声を耳にすることが増 […]
-

2025.9.25
相続
【相続の基礎知識】流れ・手続き・必要書類を徹底解説
相続とは?相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人が受け継ぐことです。財産には不動産・預金・株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続の流れ相続開始(被相続人の死亡)遺言書の確認 […]
-

2025.9.25
生前対策
【生前対策の重要性】相続トラブルを防ぐための賢い準備法
生前対策とは?生前対策とは、自分が元気なうちに財産や生活を整理し、死後に備える準備のこと。日本では相続をめぐる「争族」が社会問題化しており、早めの対策が重要です。生前対策のメリット相続税対策贈与や保険を活用することで、相 […]
