遺産相続に必要な手続きの期限一覧!期限内にできなかった場合は?
遺産相続の手続きには、期限が定められているものがあります。期限内に行わないとさまざまなデメリットが生じるため、できるだけ早く手続きをすませることが重要です。遺産相続の手続きは多岐に渡り、慣れない人にとっては、複雑で困難なケースもあります。
本記事では、遺産相続の手続き期限について、詳しく解説しています。期限を過ぎた際のペナルティについても紹介しているので、相続手続きの具体的な期限ついて知りたい方はぜひ参考にしてください。
遺産相続に必要な手続きの期限とは
遺産相続の手続きは多数あり、それぞれに期限が定められています。中には、早急に手続きを済ませなければならないものもあるので、計画的に進めることが重要です。
| 期限 | やるべきこと |
| 1週間以内 | 死亡届・火葬許可申請書 |
| 2週間以内 | 健康保険資格喪失 |
| 世帯主の名義変更 | |
| 3か月以内 | 相続放棄 |
| 限定証人 | |
| 4か月以内 | 準確定申告 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 |
| 2年以内 | 高額療養費の申請 |
| 死亡保険金の請求 | |
| 3年以内 | 相続登記 |
| 5年10か月以内 | 相続税の還付請求 |
なお、手続きの詳細は「相続の手続きの流れを理解しよう|必要書類や手順をわかりやすく解説」でも詳しく解説しています。
【死後1週間以内】死亡届・火葬許可申請書
死亡届は1週間以内に届け出る必要があります。死亡届とは、人の死が確認された際に、自治体の役所へ提出する書類のことです。
人が亡くなると、病院の医師から「死亡診断書」または「死亡検案書」が発行されます。その文書を添付し、届出書を作成して、役所へ届けます。また、死亡届を出す際は、火葬許可申請書も同時に提出しましょう。遺体は火葬許可証がないと、火葬場での焼却ができません。
なお、外国で亡くなったときは、その事実を知った日から3か月以内に申請する必要があります。
【死後2週間以内】年金受給停止
人は亡くなると、年金を受け取る権利がなくなります。そのため、遺族は、「受給権者死亡届(報告書)」を提出し、年金受給停止の手続きを取らなければなりません。国民年金の場合は死後2週間以内、厚生年金は10日以内に、年金事務所か年金相談センターで手続きします。その際には以下の書類を持参してください。
- 死亡届(基礎年金番号と年金コード、死亡年月日や生年月日などを記入)
- 亡くなった方の年金証書
- 戸籍抄本または住民票の除票など
提出が遅れると、余分に受け取った分を、後日返還する必要があります。
【死後2週間以内】健康保険資格喪失
国民健康保険や社会保険、後期高齢者医療保険等の保険証は、亡くなった時点で資格喪失します。死後2週間以内に、返却手続きをとらなければなりません。
返却先は以下のとおりです。
| 保険証 | 返却先 |
| 国民健康保険 | 市町村役場 |
| 国民健康保険高齢受給者証 | |
| 後期高齢者医療被保険者証 | |
| 健康保険証 | 職場 |
手続きの際に必要なものは以下のとおりです。
- 死亡届
- 世帯主の印鑑
- 本人確認書類
なお、健康保険に加入している場合は、死亡の翌日から5日以内に手続きする必要があります。
【死後2週間以内】世帯主の名義変更
世帯主が亡くなった場合の名義変更は、2週間以内に行わなければなりません。新しく世帯主になる人や、亡くなった世帯主と同一世帯に住んでいる人が、申請できます。代理人を立てる場合は、委任状が必要です。
世帯主の名義変更で必要になるものは以下のとおりです。
- 世帯変更届
- 本人確認書類
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 委任状(代理人の場合)
なお、全ての世帯で世帯主の名義変更が必要となるわけではありません。
- 世帯員がいない
- 世帯員が1人のみ
- 世帯員と15歳未満の子どものみ
以上のような場合、世帯主の名義変更は必要ありません。
【死後3か月以内】相続放棄
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。相続放棄とは、相続人が相続を拒否する手続きのことです。もし期限内に手続きをしなかった場合、法律上、単純承認を選択したとみなされます。単純承認とは、プラスもマイナスも含め、被相続人が残した財産をすべて相続することです。
なお、手続きの期限は決まっていますが、期間の延長の申請も可能です。被相続人の最後の住所地がある家庭裁判所に申し立てをします。詳しくは裁判所のホームページを参考にしてください。
【死後3か月以内】限定承認
限定承認とは、相続によって得る財産の範囲内でのみ、故人の債務(借金)を引き受けることです。つまり、財産のプラスもマイナスも得るものの、マイナスがプラスを超えない範囲で相続します。よって、限定承認を選ぶと、故人の財産を超える債務は負いません。
相続放棄と同じように、3か月以内に申請しないと、単純承認が成立します。なお、期限の伸長もできます。
【死後4か月以内】準確定申告
準確定申告は4か月以内に手続きをすませましょう。
準確定申告とは、個人が亡くなった場合にその人の所得税を申告し、納税する手続きのことです。故人が生前に得た収入や所得についての税金は、通常の確定申告と同様に申告します。対象となるのは、故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得です。
ただし給与所得者で年末調整を受けている、年金の収入が400万円以下などの場合、準確定申告は不要です。
【死後10か月以内】相続税の申告・納付
相続税の申告と納付の期限は、10か月以内です。後述していますが、正当な理由なく申告・納付しないと延滞税がかかるので注意しましょう。ただし、中には相続税の支払い義務がない人もいます。申告が不要なケースは以下のとおりです。
- 相続する金額が3000万円以下である
- 相続する金額が基礎控除以下である
- 各種控除を適用した場合、税額0円である
相続税の対象となる財産は、預貯金や現金、不動産や有価証券などを含みます。相続税の計算や申告書の作成は複雑なため、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
【死後1年以内】遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求できるのは、1年以内です。遺留分侵害額請求とは、相続人が最低限保障される相続財産の取り分である「遺留分」が侵害された場合、その不足分を取り戻すために、他の相続人や受遺者(遺言により財産を受け取った人)に対して行う請求のことです。
例えば、被相続人が愛人へ全財産を譲ると遺言書に記しても、相続人には法的に保障された遺留分が認められます。その遺留分が侵害されている場合には、愛人に対してその不足分を請求できるのです。
【死後2年以内】高額療養費の申請
高額療養費の申請の期限は、2年以内です。
高額療養費制度とは、医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が健康保険から払い戻される制度です。相続における高額療養費も同じで、故人が生前に支払った医療費が高額だった場合、その超過分を相続人が申請して受け取れます。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者だった場合は、役所の担当窓口で申請できます。健保の加入者だった場合は、健康保険組合へ申請しましょう。
【死後3年以内】死亡保険金の請求
死亡保険金を請求できる期限は3年以内です。この期限は保険法によって定められており、時効によって権利は消滅すると書かれています。
ただし、保険会社によっては、3年を経過しても請求できる場合があります。また、ルールでは3年と定めていても、都度相談すれば臨機応変に対応してもらえるケースも少なくありません。
とはいえ、先延ばししても不安やストレスが増すだけです。後回しにせず、早めに保険会社へ相談しましょう。
【死後3年以内】相続登記
相続登記の期限は3年以内です。
相続登記とは、相続によって得た不動産の所有権を法的に登録する手続きのことで、2024年4月1日から義務化されました。相続登記しないと不動産を差し押さえられたり、売却できなくなったりする恐れがあります。
相続登記は複雑な手続きが伴ないます。相続に関する知識と時間に余裕がない場合は、司法書士や弁護士など、専門家への依頼がおすすめです。
【死後5年10か月以内】相続税の還付請求
相続税の還付請求の期限は、5年10か月以内です。
相続税の還付請求とは、支払った相続税が多すぎた場合に、その過剰分を国から返してもらう手続きのことです。例えば、遺産の評価額を高く見積もりすぎたり、後から新たな非課税の財産が見つかったりした場合は、支払った相続税が本来より多くなってしまうことがあります。
申請では必要書類を揃え、税務署へ届けましょう。還付請求が認められると、過剰に支払った相続税が指定した口座へ返金されます。
期限がない遺産相続に必要な手続き
手続きに期限がない遺産相続もあります。とはいえ、放置すると相続人間でのトラブルが発生したり、相続財産の価値が下がったりする可能性があります。そのため、早めに手続きを進めることが重要です。
遺言書の検認
遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在や中身を確認することを指します。遺言書の検認では、特に期限が定められていません。しかし、検認が行われない限り、遺言書の内容に基づいた相続手続きを進めることができません。
つまり、遺言書があっても検認されるまでその効力は発揮されないため、早めに家庭裁判所へ検認の申し立てを行いましょう。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、被相続人の遺産を相続人同士でどのように分割するかを話し合い、合意する手続きのことです。
法的に明確な期限は定められていませんが、相続税の申告と納税は相続の開始(通常は被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。この期限までに遺産分割協議がまとまっていない場合、未分割の財産については法定相続分に基づいて相続税を計算しなければならず、不利になることがあります。
また、遺産分割協議が長引くと、相続人間での意見の対立やトラブルにつながるため、早めに話し合うことが望ましいでしょう。
銀行口座の名義変更
銀行口座は、名義人が亡くなると凍結されます。名義変更の手続きを行わないと、口座からの引き出しや預金の解約ができません。手続きに期限はありませんが、相続税の申告・納付は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければならないので、それまでに済ませたいものです。
万が一、亡くなったあとに銀行名義を変更しないまま預金を引き出すと「単純承認」とみなされる可能性があります。単純承認を選択すると、マイナスの財産まで相続しなければならないため、負債が多い場合は特に注意が必要です。
遺産相続手続きを期限内にしなかった場合はどうなる?
期限内に遺産相続手続きをすませないと、さまざまな不都合が生じます。通常よりも支払う金額が多くなったり、手続きの手間が増えたりと、良いことは何もありません。
ここでは、期限内に手続きをしないことで起こりうるデメリットについて解説します。
相続税の延滞税がかかる
相続税の申告・納付の期限が過ぎると、延滞税がかかります。延滞税は、期限内に納付されなかった相続税に対して年率で利息が加算されるので、納税額が増えることになります。
延滞税の率は法定利率によって決められており、納税が遅れるほど金額が増加します。そのため、納付を先延ばしにすればするほど、相続税の負担がさらに重くなります。
延滞税の割合は以下のとおりです。
| 納付期限の翌日〜2か月を経過する日まで | 年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方 |
| 納付期限の翌日から2か月を経過した日以降 | 年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方 |
なお、国税庁のホームページでは最新の情報が紹介されているので、あわせてご覧ください。
税の軽減制度が利用できなくなる
税金の申告・納付の期限が過ぎると、軽減制度が利用できなくなります。
例えば、「小規模宅地等の特例」では、被相続人が住んでいた自宅や事業用の土地について、一定の要件を満たす場合、評価額が最大80%減額されます。ただし、期限内(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに申告を行う必要があります。期限を過ぎると、この特例は利用できません。
また、「配偶者控除」では、配偶者が取得する相続財産について、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税が非課税となります。ほかにも「未成年者控除」では相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
これらの控除も期限内に行うことが前提です。
過料の制裁が科される
一部の手続きでは、期限を守らない場合に過料という形で制裁が科されることもあります。例えば、相続登記を怠った場合です。正当な理由もなく、相続を知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性もあります。この場合の正当な理由とは、相続人の病気や相続の複雑さ、経済的・法的問題などです。
なお、遺言書の検認に期限はありませんが、検認する前に開封してしまうと、5万円以下の過料が課されることもあるので注意しましょう。
新たな相続が発生する
遺産相続手続きを期限内にしなかった場合、新たな相続が発生する可能性もあります。例えば、遺産分割協議をする前に相続人が亡くなることで、次の相続が発生するケースです。
新たな相続が発生すると、手続きがさらに複雑になります。また、相続手続きが重複すると、相続登記や相続税の申告などの手続きを複数回行う必要が出てきます。そうすると、手続きにかかる時間や費用が増加する恐れもあるのです。
このように、新たな相続が発生した場合には、手続きがさらに複雑化し、相続人同士のトラブルや費用の増加などのトラブルにつながる可能性があります。
遺産相続手続きは「相続の窓口」におまかせください
遺産相続の手続きは、種類がたくさんあり、相続が発生してから短い期間ですませなければならないものもあります。慣れない手続きで大変ですが、本記事を参考にして期日内に終わらせることをおすすめします。相続手続きでお困りのことがあれば、行政書士や専門家に相談しましょう。広島・福山・北大阪のご相談や手続きなら、「相続の窓口」におまかせください。相続手続きの経験豊富な行政書士が、親身になってお悩みを解決します。
ARTICLE 記事コンテンツ
-
遺族年金の手続き方法と期限
家族が亡くなった場合、遺族年金を受給できる可能性があります。遺族年金を受け取ることで、今後の経済的な不安を軽減することにつながります。今回は、遺族年金の手続き方法と手続きの期限について、解説していきたいと思います。遺族年 […]
-
遺留分を考慮した生前対策の方法とは
遺留分とは、一定の相続人に認められた、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合のことをいいます。財産を受け渡す側が財産を特定の相続人などに移転させるために、遺留分についてできる対策はどのようなものがあるのでしょうか […]
-
公正証書遺言を作成するメリットと作成手順
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があり、それぞれ法律で定められた手順で作成していく必要があります。今回は、公正証書遺言を作成するメリットと作成手順について解説していきたいと思います。紛失や偽造の […]
NEWS・COLUMN お知らせ・コラム
-
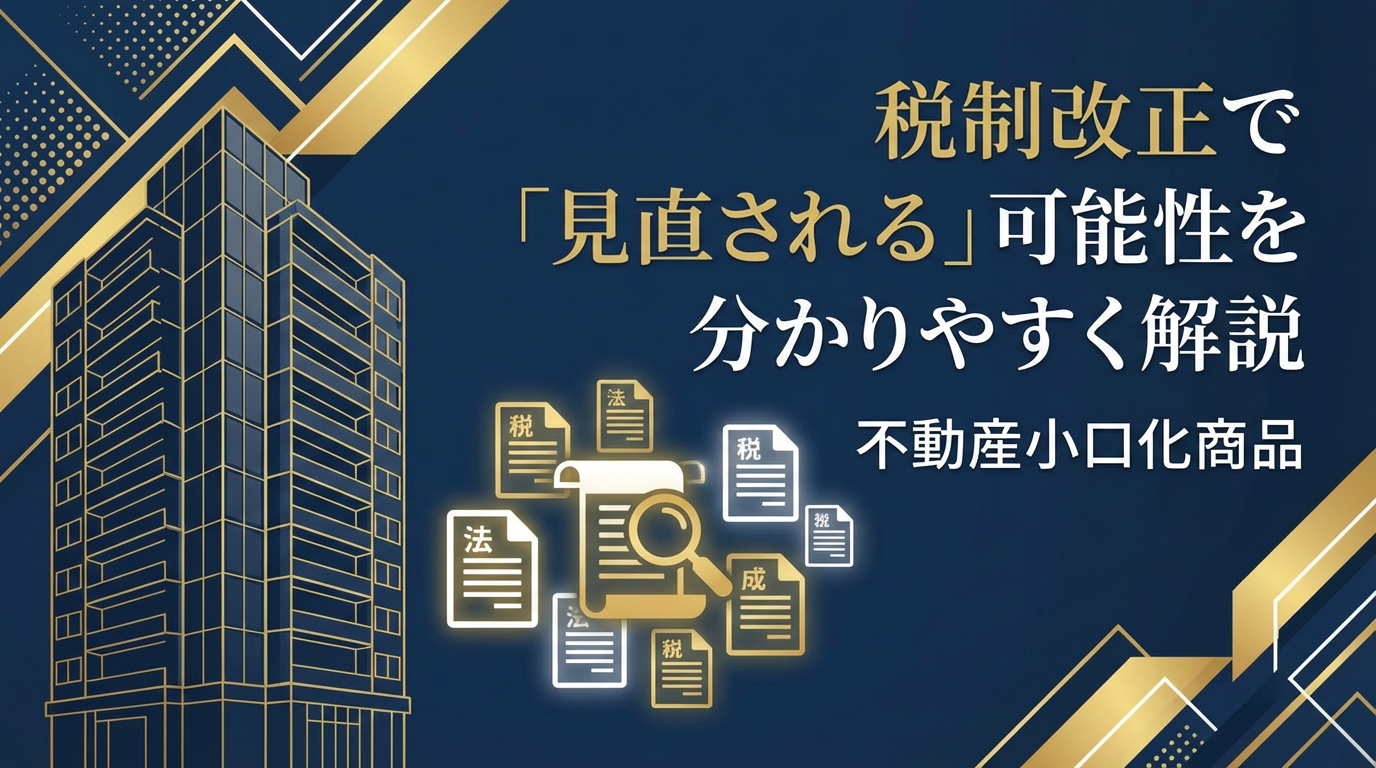
2025.12.14
生前対策
終活
不動産小口化商品による相続対策は今後どうなる?
税制改正で「見直される」可能性を分かりやすく解説相続対策として注目されてきた「不動産小口化商品」について、最近になって「将来、相続対策として使えなくなるのでは?」「無効になるという噂を聞いた」といった声を耳にすることが増 […]
-

2025.9.25
相続
【相続の基礎知識】流れ・手続き・必要書類を徹底解説
相続とは?相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人が受け継ぐことです。財産には不動産・預金・株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続の流れ相続開始(被相続人の死亡)遺言書の確認 […]
-

2025.9.25
生前対策
【生前対策の重要性】相続トラブルを防ぐための賢い準備法
生前対策とは?生前対策とは、自分が元気なうちに財産や生活を整理し、死後に備える準備のこと。日本では相続をめぐる「争族」が社会問題化しており、早めの対策が重要です。生前対策のメリット相続税対策贈与や保険を活用することで、相 […]
