遺族年金の手続き方法と期限
家族が亡くなった場合、遺族年金を受給できる可能性があります。
遺族年金を受け取ることで、今後の経済的な不安を軽減することにつながります。
今回は、遺族年金の手続き方法と手続きの期限について、解説していきたいと思います。
遺族年金の手続き方法
遺族年金は以下のような流れで手続きをすすめていきます。
- 年金請求書を記載する
- 必要書類の準備
- 年金証書と年金決定通知書を受け取る
それぞれ確認していきたいと思います。
年金請求書を記載する
年金請求書とは、亡くなった方と遺族年金を請求する方の情報を記入するための書類です。
亡くなった方の氏名や生年月日などの基本的な情報から、公的年金制度の加入履歴やその他必要な情報などを詳細に記載していくことになります。
年金請求書は、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。
必要書類の準備
年金請求書には以下のような必要書類を添付する必要がありますので、添付書類について準備をする必要があります。
- 基礎年金番号通知書や年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
- 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
- 世帯全員の住民票の写し
- 請求者と子どもの収入がわかる書類
- 死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- 振り込みを希望する口座の通帳またはキャッシュカード
年金請求書と上記の必要書類が準備できたら、郵送などによって提出していくことになります。
年金証書と年金決定通知書を受け取る
年金請求を行うと、日本年金機構から年金証書と年金決定通知書が送付されます。
年金証書とは、年金を受給する権利を持っていることを証明するものです。
書類には基礎年金番号が記載されており、年金に関連する手続きを行う際に必要となることがあります。
年金決定通知書とは、支給される年金の額が決定された際に送付されるものです。
書類には、受給する年金の具体的な金額が記載されています。
手続きの期限
遺族年金の請求期限は、生計を維持していた人が亡くなった翌日から5年以内です。
ただし、時効が消滅しないようにするために、理由を書面で記載して申立て手続きをすれば、時効期限が延びる場合もあります。
まとめ
今回は、遺族年金の手続き方法と手続きの期限について、確認していきました。
遺族年金の請求手続きには多くの書類や手間が必要となります。
自身で手続きを進めるのが難しい場合には、社会保険労務士に相談することを検討してみてください。
ARTICLE 記事コンテンツ
-
遺族年金の手続き方法と期限
家族が亡くなった場合、遺族年金を受給できる可能性があります。遺族年金を受け取ることで、今後の経済的な不安を軽減することにつながります。今回は、遺族年金の手続き方法と手続きの期限について、解説していきたいと思います。遺族年 […]
-
遺留分を考慮した生前対策の方法とは
遺留分とは、一定の相続人に認められた、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合のことをいいます。財産を受け渡す側が財産を特定の相続人などに移転させるために、遺留分についてできる対策はどのようなものがあるのでしょうか […]
-
公正証書遺言を作成するメリットと作成手順
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があり、それぞれ法律で定められた手順で作成していく必要があります。今回は、公正証書遺言を作成するメリットと作成手順について解説していきたいと思います。紛失や偽造の […]
NEWS・COLUMN お知らせ・コラム
-

2026.2.22
生前対策
終活
【令和8年度税制改正】相続税・贈与税の実務はどう変わる?資産別解説
令和8年度税制改正により、相続税・贈与税の実務に影響を与える見直しが行われました。特に重要なのは、不動産評価の見直し、教育資金一括贈与の非課税措置の終了、事業承継税制の計画提出期限の延長です。本記事では改正内容を正確に整 […]
-
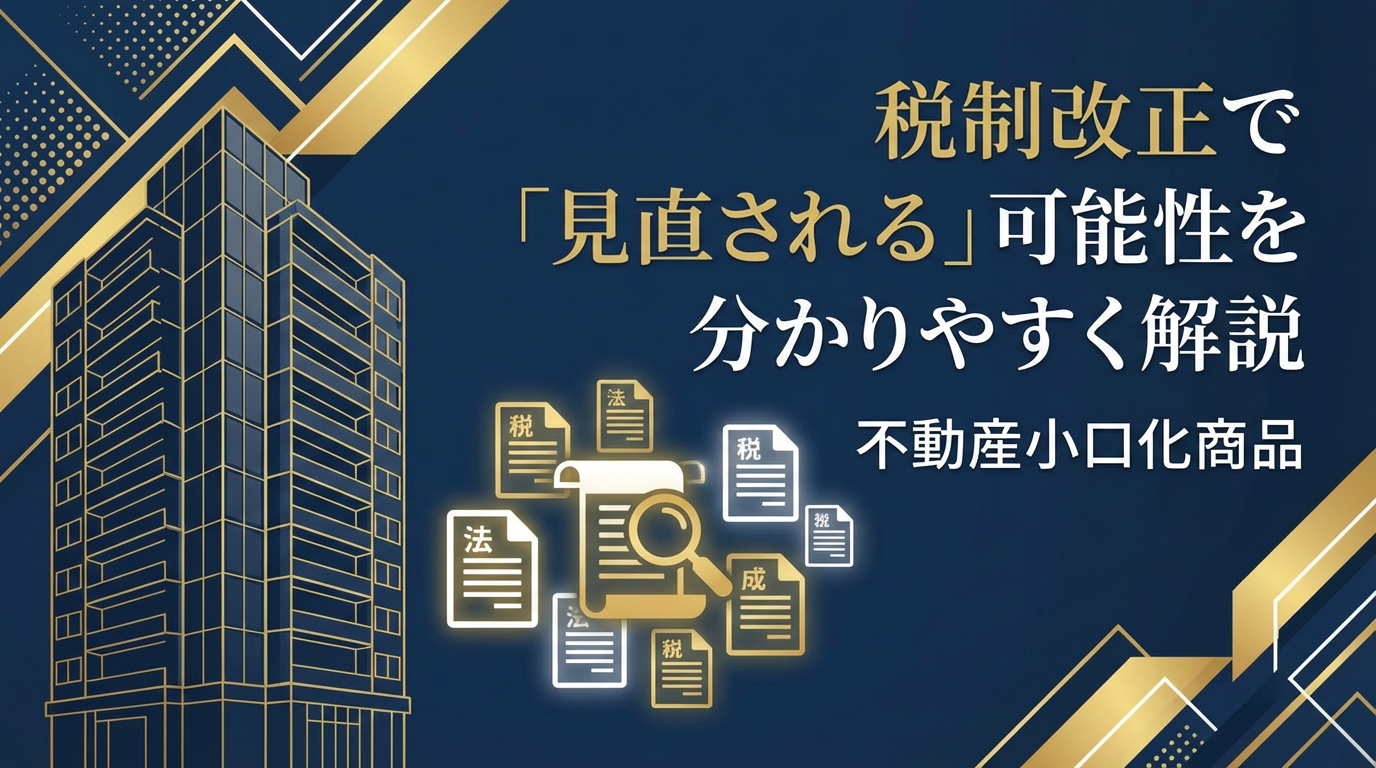
2025.12.14
生前対策
終活
不動産小口化商品による相続対策は今後どうなる?
税制改正で「見直される」可能性を分かりやすく解説相続対策として注目されてきた「不動産小口化商品」について、最近になって「将来、相続対策として使えなくなるのでは?」「無効になるという噂を聞いた」といった声を耳にすることが増 […]
-

2025.9.25
相続
【相続の基礎知識】流れ・手続き・必要書類を徹底解説
相続とは?相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人が受け継ぐことです。財産には不動産・預金・株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続の流れ相続開始(被相続人の死亡)遺言書の確認 […]
